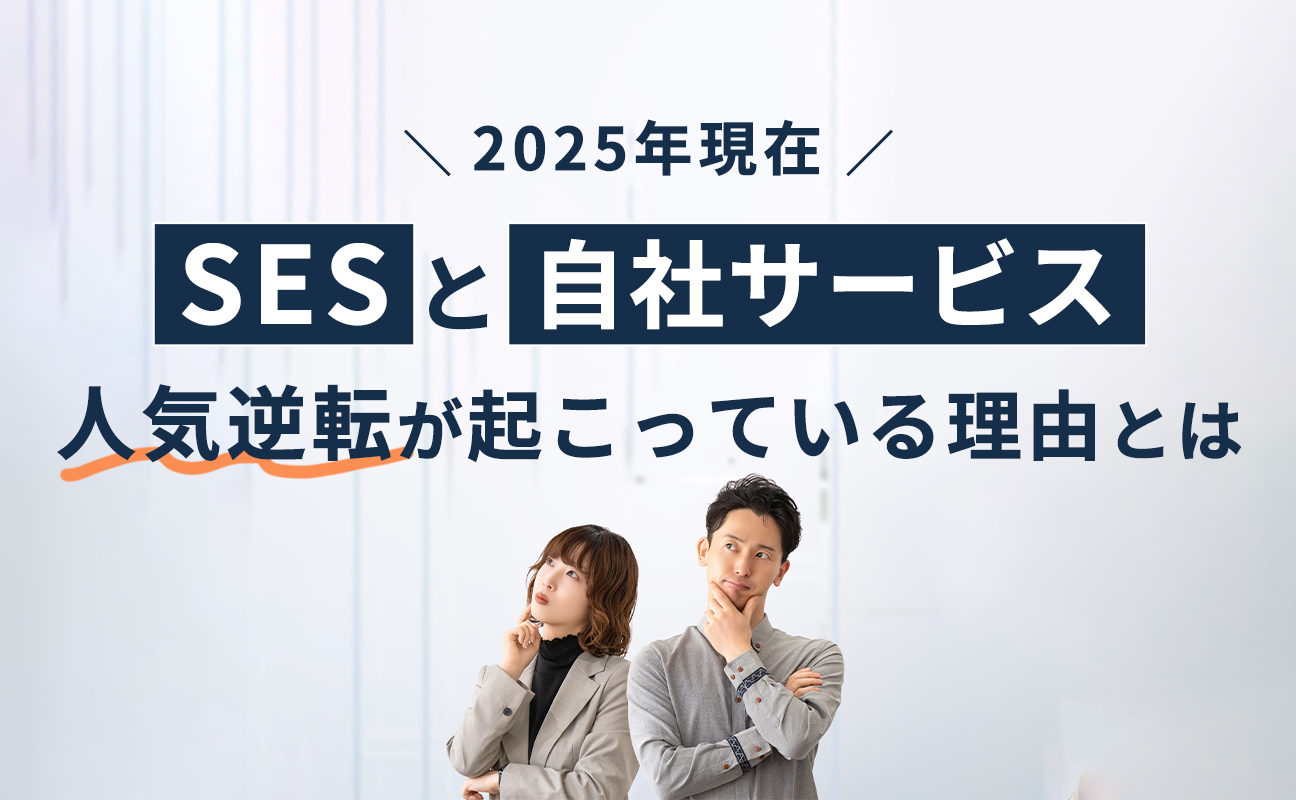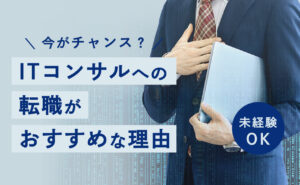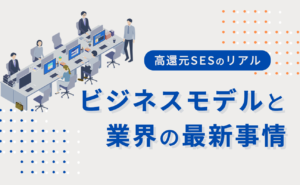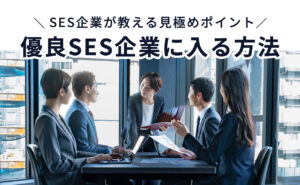こんにちは、セルバコンサルティング採用広報のゆうきです。
かつて若手エンジニアの就職・転職先として圧倒的人気を誇っていたのは『自社サービス企業』でした。
自分たちのプロダクトを育て、技術的なチャレンジができる環境。そんなキラキラしたイメージが、多くのエンジニアの心を惹きつけていました。

しかし、2025年現在はその流れに変化が起きています。
2020年前後までの自社サービス >>> 受託 >>> SESというヒエラルキーがあった時代から、SESが静かに再評価されつつあります。
SESが若手エンジニアに選ばれている理由

SESって結局下請けでしょ?



SESは案件ガチャ。
少し前まではSESにそういうイメージがあり、SESというだけでエンジニアの確保に苦労していた時期もありました。
しかし2025年現在、なぜSESが再評価されているのか。その理由を解説します。
フリーランス志向との親和性
SESの現場は基本的にクライアントワークです。
自分が“外部パートナー”として関わるというスタンスなので、将来独立したい人にとっては絶好の訓練になります。
- タスクの自己管理:誰かに細かく指示されるのではなく、自分で優先順位をつけて進める場面が多い
- 報連相の実践力:適切な頻度・方法での報告や相談が求められるため、クライアントとの信頼構築の経験が積める
- 納期意識の強化:SESでは準委任契約が一般的なものの、クライアントにも都合があるので、期限内に成果を出す姿勢が求められる
これらはすべて、フリーランスとして働く際に不可欠です。
SES現場での実践経験が、そのまま「仕事がもらえるフリーランスエンジニア」としての力につながっていきます。
ITコンサルに転職しやすい
最近はITコンサル企業が急成長を遂げています。
たとえばベイカレント、ディルバート、ノースサンドといった新興ITコンサル企業は、年収面でも働き方の柔軟性からも若手に人気です。
実は、SES出身のエンジニアはITコンサルに転職しやすいという事実があります。
その理由は「ITコンサルに必要な知識があり、クライアントワークに慣れている」が主な理由ですが、それだけではありません。
- 現場適応力が高い:プロジェクトごとに異なる業務環境・チームに順応する経験を積んでいるため、ITコンサルが関わる多様なクライアント企業への対応力が高い
- 技術とビジネスの橋渡し経験:技術的な知見を活かしつつ、現場でビジネス部門と調整する機会が多く、コンサルに求められる“翻訳力”が身につきやすい
- ヒアリングと提案の実務経験:要件定義や追加要望の吸い上げ、改善提案など、提案型の仕事にも自然と関わっているケースが多い
SES出身のエンジニアは、こうした「技術だけではない視点」と「クライアント視点での柔軟な対応力」が備わっている傾向があるので、“ITコンサルに適した人材”として歓迎されています。
自社サービス企業の停滞
2010年代は、メルカリやSmartHR、freeeなどの“メガベンチャー”が次々と誕生した時代でした。
スマホの普及やSaaS、クラウドといった新しい技術領域がビジネスの追い風となり、多くの若手エンジニアがその成長環境に魅了され、自社サービス企業は圧倒的な人気がありました。
しかし、2020年代に入ってからはその勢いに陰りが見えています。
ここ数年で“ITメガベンチャー”と呼ばれるような企業はほとんど誕生していません。
サービスは成熟し、新規性のある差別化が難しくなり、プロダクトの改良や運用フェーズに注力せざるを得ない企業が増えています。
その結果、エンジニアにとっては新たな技術チャレンジやスケールアップの機会が減少し、“成長実感”が得にくくなってきているのが現実です。
自社サービス企業出身のエンジニアが抱える課題
自社サービス企業が圧倒的人気を誇っていたことから、自社サービス企業出身のエンジニアは上位層で優秀なイメージがありますが、意外な弱点もあります。
基本的に自社サービスの開発・運用は社内で完結するため、ビジネス部門や営業チームとの分業体制が確立されています。
そのため、ユーザーの要望や現場の声に直接触れる機会が少なく、技術的な意思決定も社内の都合が優先されがちです。
顧客対応や要件ヒアリングといったクライアントワーク特有のスキルが身につきにくく、転職市場では「実務経験は豊富でも、応用力やビジネス感覚に乏しい」と見なされることがあります。
結果として、自社サービス企業出身のエンジニアは年収が伸び悩むケースも少なくなくなってきました。
SESのヒエラルキーが低かった2010年代
2010~2020年前後は、SESのヒエラルキーが特に低かった時代です。
なぜSESのヒエラルキーが低かったのか、その背景を説明します。
SESに対するネガティブなイメージの定着
2000年代〜2010年頃までのSES企業の多くは、技術力の育成よりも人月単価での収益最大化を目的とするビジネスモデルが主流でした。
いわゆる「人材派遣的なアサイン」が中心で、エンジニア個人のスキルや希望よりも、営業力や価格競争力が重視される傾向が強かったのです。
その結果、「クライアント企業に常駐して言われたことをやるだけ」「下流工程が多く、成長機会が少ない」といったSESに対するネガティブなイメージが定着しました。
企業や営業の都合優先で案件が決まるためどの現場に配属されるかがわからない“案件ガチャ”や、エンジニアの意に反した案件に長期常駐させられる“人売り”的な実態がSNSやブログで可視化されたこともあり、若手エンジニアの就職先としてSESは敬遠されがちでした。
自社サービス企業・スタートアップが脚光を浴びた時代
2010年代前半から中盤にかけて、自社サービス企業やスタートアップの成長が加速しました。
スマートフォンの普及やクラウドサービスの浸透を背景に、メルカリ、SmartHR、freee、Wantedlyといった企業が続々と登場。新しいサービスやUI/UX、モダンな技術スタックを武器に急成長を遂げ、メディアやSNSでも注目を集めました。
この流れの中で、若手エンジニアたちは「自分たちの手でサービスを作る」「社会にインパクトを与える」という理念に強く惹かれ、従来のSESや受託開発よりも自社開発企業を志望する傾向が顕著になっていきます。
技術選定の自由度やアジャイルな開発プロセス、裁量ある働き方といった要素も相まって、エンジニアとしての理想を叶える環境として高く評価されていました。
フリーランス・副業ブームの前兆
2010年代後半から、副業解禁や働き方改革、案件獲得ができるプラットフォーム(クラウドワークスやランサーズ、Wantedlyなど)の普及によって、フリーランスや副業に対する世間の関心が徐々に高まっていきました。
特にTwitterやQiitaといった情報共有メディアでは、「自由に働くフリーランスエンジニア」への憧れがトレンドとして盛り上がっていた時期でもあります。
しかし、当時のSESに対する一般的なイメージはそれとは正反対のものでした。
- 常駐先での勤務時間・場所に制限される
- アサイン先の決定権がエンジニアになく、希望はほぼ通らない
- 長期常駐が前提となるためスキルが頭打ちになり、キャリアアップがしづらい
このような点から、SESは「自由に働く」というより「拘束される働き方」と捉えられ、フリーランス志向の若手からは敬遠されがちでした。
ただし、2020年以降は徐々にリモートワーク・副業解禁などを背景に、SESの柔軟性やキャリアパスの多様性が見直されるようになっていきます。
加えて、SNSや企業口コミサイトの普及により、いわゆる“ブラックSES”と呼ばれるような悪質企業の実態が可視化され、業界全体の健全化も進みました。
待遇改善や教育体制の整備、案件選択制などの取り組みを通じて、「キャリアアップできるSES企業」も確実に増えてきています。
セルバコンサルティングはITコンサル案件・ITコンサルへの転職に強みがあります



SESって結局、下請けでしょ?
そんなイメージが少し前までは主流でしたが、2025年現在、SESはITコンサルやフリーランスといった次のキャリアへと続くステップとして、再評価されています。
セルバコンサルティングでは、SES事業とITエンジニア向けの転職支援を行っています。
特にITコンサル案件に強みがあり、「エンジニアからITコンサルにキャリアチェンジしたい」「年収をもっと伸ばしたい」といった方のサポート実績も多数あります。
ITコンサルへの転職を目指す方、よりよい案件でスキルアップしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。