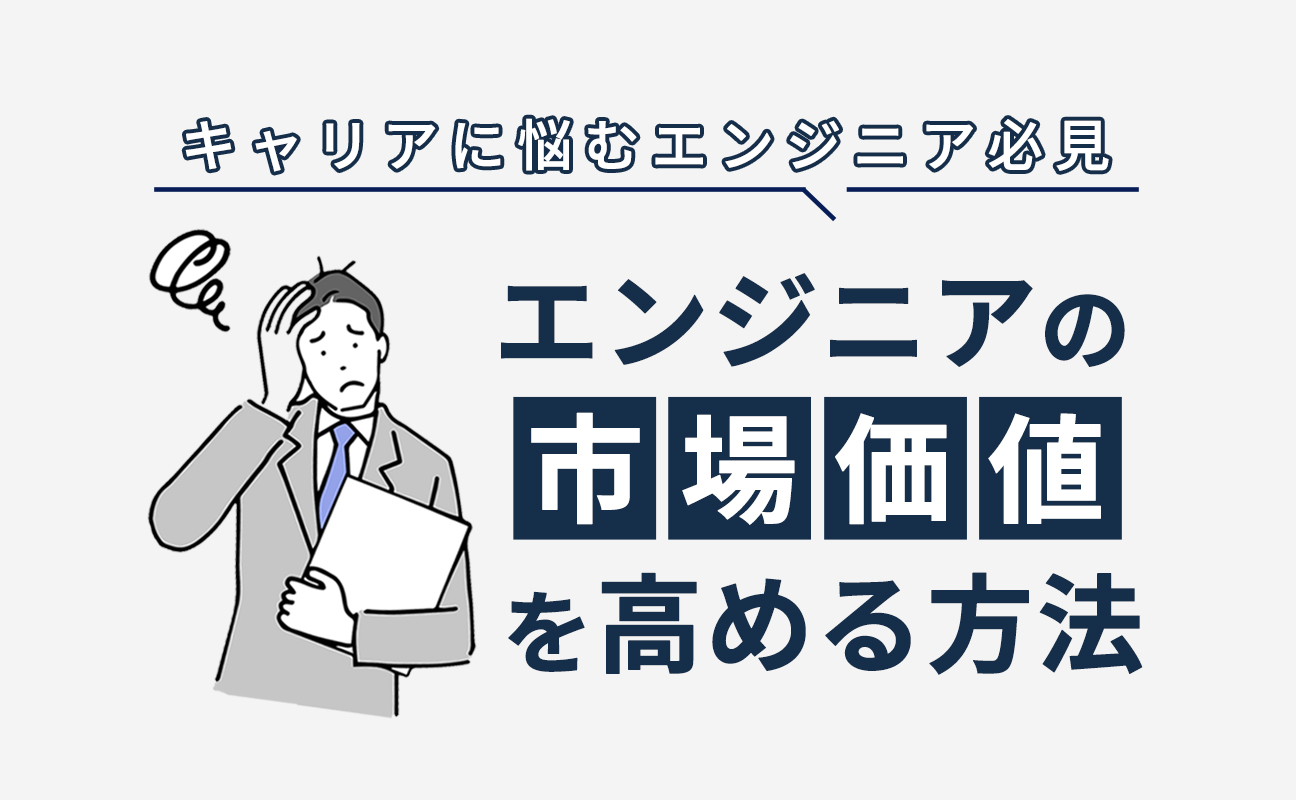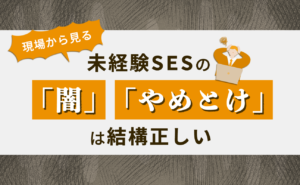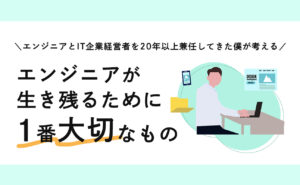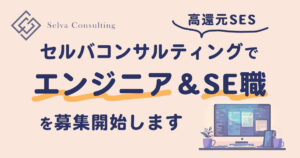こんにちは。セルバ/セルバコンサルティング代表の中山です。
先日、ある若手エンジニアから転職の相談を受けました。
話していく中で出てきたキーワードが

自分の市場価値を上げたい。
「市場価値って何だと思いますか?」と質問したところ、返ってきたのは「プログラミングスキルですかね」という答え。
これは若手エンジニアによくある思い込みです。
残念ながら、プログラミングスキルが評価されるのは開発経験5年くらいまでで、それ以降はプログラミングスキルが高くなっても市場価値が上がるわけではありませんし、開発経験の年数に比例して市場価値が上がるわけでもありません。
多くのエンジニアが「市場価値を上げたい」と言いますが、そもそもそれが何を意味するのかを言語化出来ていません。
僕もエンジニア比率が7割以上の会社(セルバ)を20年以上経営しているので、キャリアの選択に迷い、やみくもに短期間で転職を繰り返してしまう求職者、転職支援希望者を多く見てきました。
今回の記事では「市場価値とは何か?」を明確にし、どうすればエンジニアが市場価値を上げられるのかについて、現役のエンジニアでもあり、エンジニアを雇用する側でもある僕の視点からお届けします。
※セルバコンサルティングではSES事業も行っています。
案件と人材の数がN:N(極端な偏りがない)の場合、相場感としては以下になります。
①エンジニア経験1年~
単価:40万~50万
給与:25万~35万
※プログラム開発1年目
②エンジニア経験3年~
単価:50万~70万
給与:30万~45万
※プログラム開発3年目
③エンジニア経験5年~
単価:60万~80万
給与:35万~55万
※基本設計以降~、部下1~2名
以降は要件定義、マネジメント経験によって単価が増える
- プログラム開発経験は、5年目以降はあまり単価・年収に反映されない
5年目以降は要件定義、マネジメント経験、ビジネスドメインに詳しいかが単価を左右する - 3~5名のマネジメント経験 プラス10万円~
- 数千万円規模の要件定義経験 プラス10万円~
- ビジネスドメインに詳しいか プラス10万円~
- 数億円~のシステムのPL、SE 単価100万を余裕で越える
- 「市場価値」の正体
- 市場価値と年収の相関性
- エンジニアが市場価値を高める具体的な方法
- スキルアップの落とし穴
- 自社開発とSESのリアルな違い
- 転職のベストなタイミング
そもそも「市場価値」とは何なのか
結論から言うと、市場価値とは「今の自分に世間がどれだけお金を払ってくれるか」です。
社内でどれだけ評価が高くても、それが内輪のルールに基づいたものなら、市場に出たときに通用しません。
(従来の終身雇用型の企業しか経験したことがない人は、このケースに陥ることが多いです)
逆に、今の社内での評価がそこまで高くなくても、複数社からオファーが来るなら、それは市場価値が高いということです。
市場価値は、「他社からのニーズがどれだけあるか」で決まります。
シビアな判断軸ですが、だからこそ自分のキャリアを見直すヒントにもなります。
現在の年収=市場価値ではない
たとえば、「年収800万でスカウトがまったく来ないAさん」と、「年収500万でスカウトがひっきりなしに届くBさん」がいたとします。
社内で高く評価されているのはAさんですが、転職市場で高く評価されているのは間違いなくBさんです。
「社内での地位」より「他社からのニーズ」こそが市場価値。
年収はあくまで結果論に過ぎません。
「どこに求められたいのか」を明確にする
React、Next.js、Docker。学ぶべきITの技術は山ほどあります。
でもそれは、「自分が行きたい企業」で求められているスキルでしょうか?
今、多くの企業が求めているのは、“特定の言語で難解なコードが書ける人”や“画期的なアルゴリズムを開発できる人”より、以下のような“現場で物事を前に進められる人”です。
- 要件定義や設計が出来る人
- クライアントと擦り合わせが出来る人
- 期限を意識してマネジメントが出来る人
「どんな企業に求められたいのか」を意識することで、自分の伸ばすべきスキルが明確になります。
難解なコードが書ける人や、画期的なアルゴリズムを開発できる人を求めている企業も中にはあると思うので、「プログラミング以外はやりたくない。技術を極めたい」というのであれば、技術に特化する道もあります。
しかし現実として、現在の転職市場でニーズがあるのは“現場で物事を前に進められる人”です。
市場価値を高める4つの要素
これまで多くの転職相談に乗ってきた経験から言うと、以下の4つを意識することが非常に重要だと感じています。
大きく成長している業界・分野
業界・分野が大きく成長していると、需要に対して人材の供給が追いついていないので、個人のスキルや経験が自然と高く評価されやすくなります。
企業は人材を確保するために好条件を提示するので、転職市場でも引く手あまたですし、先行者が社内に少ないので、実務を通じて責任のある業務を任せてもらいやすくなります。
最近の熱い分野なら、クラウド(AWS/GCP)、SAP、SalesForce、医療・金融・物流のDX分野、または生成AIの実装などですね。
とはいえ、今まさに成長業界にいるからといって安心は出来ません。
ITやWEB業界は特に「今熱い分野」の移り変わりが激しいので、常にアンテナを張っておく必要があります。
代替のきかない専門性
特定の領域において深い知見や実績がある人材は、企業にとって「その人にしかできない仕事」を任せられる存在となり、結果として報酬や待遇の交渉力も強くなります。
- 特定業界に精通している
- アーキテクチャ設計に強い
- セキュリティや法務対応まで理解している
こうした希少性×再現性のあるスキルは、市場価値が落ちません。
専門性は簡単には模倣できないため、長期的に価値が維持されやすいです。
ビジネスの成否を左右することもあり、市場からのニーズは非常に高くなります。
- 特定業界(例:金融、保険)に特化した業務知識
- インフラやアーキテクチャ設計の深い知見
- セキュリティ、認証、法務対応などの周辺スキル
専門性と聞くと「プログラミングのスキルを極めよう」とする人も多いですが、技術はどこまでいっても手段でしかありません。
手段として正しく使うためにも一定の技術力は必要ですが、生成AIなどが今後も進化していくことを考えると、“代替のきかない”ものであるとは言い難いです。
代替のきかないものでなければ市場価値を高めることは出来ません。
大きな金額を動かした実績
- 数千万円規模のプロジェクトに主要メンバーとして携わった
- 業務改善で年間数千万円のコスト削減を実現した
など、大きな金額を動かす業務に携わった実績があると、信頼性や背負った責任の重みが増し、自然と市場価値も高まります。
案件の規模が大きくなるほど判断力・分析力・交渉力が求められます。
その成果が企業や組織全体に与える影響も大きくなるため、そうした経験を持つ人材は他社からも高く評価されます。
数字で語れる成果
数字で語れる成果を出すことは、自身の実力を客観的に証明できる手段です。
売上を何%伸ばした、コストをいくら削減した、作業時間を何時間短縮したといった具体的な数値は、誰が見ても評価基準が明確で、説得力があります。
数字で語れる実績を持つ人材は「自社にもその成果をもたらしてくれそうだ」と採用の場で期待されやすく、昇進の場でも「この事業にこれだけ貢献した」ことが明確なので、有利になります。
数字は言い訳がきかないからこそ、市場価値を高める武器となります。
- CVRが2.1%→3.4%に改善
- 会員数が半年で1.8倍に増加
- バグ件数を1年で80%削減
エンジニアが市場価値を高めるために意識すべきポイント
これまで話したことは市場全体の話になるので、あまりピンとこなかった人もいるかもしれません。
市場価値を高めたいエンジニアが「今、具体的に何をすべきか」を解説します。
リーダー経験を積む
開発経験そのものが評価されるのは基本的に5年目くらいまでです。
それ以上は頭打ちになり、比例して市場価値が上がるわけではありません。
では次のステップとして何をすべきかと言うと、リーダー経験を積むことが必要になってきます。
- プロジェクトの進行管理
- メンバーの育成
- 顧客との折衝
こういった経験を履歴書や職務経歴書に書くと、数年の開発経験があるだけの人よりも一気に評価が高くなります。
まずは小さなプロジェクトでも構いません。1〜2名のタスク管理からでも良いのでリーダー経験を積みましょう。
クライアントワークの経験を積む
多くの企業が求めているのは、ただプログラミングができる人ではなく、「顧客と要件を詰めて、プロジェクトを前に進められるエンジニア」です。
社内で完結する自社サービスの開発経験しかないエンジニアよりも、社外のステークホルダーと向き合った経験があるエンジニアのほうが、“汎用性のあるスキルがある”と見なされます。
「SESではスキルがつかないから、早めに受託か自社開発の企業に転職するべき」という風潮の時期もありましたが、SESも結局は案件次第です。
運用保守の案件にばかり参画していたら市場価値は上がりませんが、ある程度経験を積んだら上流工程の案件に挑戦することでクライアントワークの経験は積めますし、そういった意味では自社開発よりもSESの方が市場価値を高めやすいといえます。
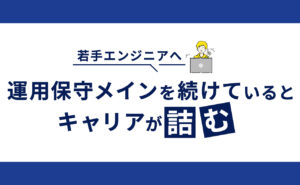
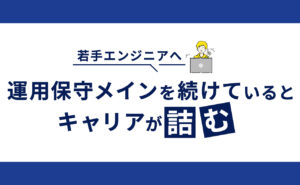
規模の大きい案件に携わる
大きな規模の案件では、以下のようなスキルや経験が手に入ります。
- 進行管理の複雑さに対応する力
- 複数のベンダーとの連携をまとめあげる力
- チームビルディングの経験
- 重要な意思決定の経験
小さな案件でも、チームビルディングやステークホルダーと調整しての開発経験は積めますが、大きな案件ほど携わる人数が多くなるため、管理が複雑化します。
大きな案件に携わった経験が転職市場で大きく評価されるのは、それが理由です。
実績を数字で語れるようにする
開発経験そのものが評価される5年目くらいまでは「こんな案件に携わりました」「この言語でこんなシステムを作りました」だけで実績を語っても良いですが、5年目以降はそれだけでは評価されにくくなります。
5年目以降は、実績を語るなら「どんな価値を出したか」を具体的な数字で伝えましょう。
- 会員数を2年間で1.8倍に拡大
- サーバーコストを月30%削減
- バグ報告件数を月50件→10件へ改善
- 全体の工数から1割削減
このような数字があるだけで、職務経歴書の説得力が一気に増します。
プログラミングスキルだけ高めても意味がない?
繰り返しますが、プログラミングのスキルはあくまで手段であって、難解なコードが書けたり複雑なアルゴリズムが開発出来れば市場価値が上がるわけではありません。
PythonやAWS、Next.jsなどの技術をどれだけ学んだとしても、それが業務の中で「どう役立ったか」が明確でないと、市場では高く評価されません。
企業が欲しているのは「課題を解決できる人材」であり、「知識量が多い人」ではないからです。
実際の面接でも問われるのは「自分のプログラミングスキルが業務の中でどう役立ったか」です。
たとえば、面接では以下のような質問をよくされます。
これに対する回答を転職時には用意しておく必要があります。



その技術を使って、どういう課題を解決しましたか?



それによって、どんな数値的改善がありましたか?



チームや顧客との連携の中で、どんな工夫をしましたか?
「成果」を伴わないスキルは評価につながらない
資格取得や書籍、Udemyなどの学習でスキルを高めること自体は素晴らしいですし、エンジニアとして必要なことです。
しかし、それを「実務にどう活かしたか」伝えられない限り、市場価値の上昇にはつながりません。
テストで良い点が取れるだけで高く評価されるのは学生までです。
学びはスタート地点に過ぎません。
市場価値を上げるには、「学んだことを、どこで・どのように・どんな成果につなげたか」を言語化できることが不可欠です。
「市場価値を上げたい」なら転職すべき?
最近は転職回数を見る企業が増えてきているので、ジョブホッパー的な安易な転職は市場価値を下げます。
まずは今勤めている会社で腰をすえて、市場価値を高められないかを考えることをおすすめします。
最近IT企業でも転職回数を見てくる企業が急激に増えた。数年前みたいに安易に転職を繰り返しているエンジニアは採用されない。エンジニアバブルは終わったんだからマインド改めないとね。
— なかやま💻セルバ / セルバコンサルティング代表 (@selva_tec) June 12, 2025
ただ、今の会社に以下のような兆候が見られたら、転職を前向きに検討するタイミングです。
特にエンジニアになって5年目以降は、これらの兆候がある会社に長くいるとキャリアが詰む可能性があるので、転職をおすすめします。
- 会社全体で下流工程や運用保守をメインとする案件しか扱っていない
- 大きな金額を動かす仕事がない
- 社内で完結する仕事ばかりで顧客折衝の経験が積めない
- チームではなく単独での仕事しか経験できず、リーダー経験が積めない
- 後輩や部下となる新人が入ってくる見込みがない
- 会社の業績が悪い、または長年停滞している
エンジニアになってまだ数ヶ月しか経っていないような人、特に新卒1年目の人は、まずは転職よりも目の前のタスクをこなしていくことを考えましょう。
未経験に近い状態ではまだこれらを見極めることは難しいですし、実務経験が数ヶ月程度では他社からのニーズもないからです。
セルバコンサルティングはエンジニアの市場価値を上げるお手伝いをします
セルバコンサルティングは転職支援者の「市場価値」を上げるお手伝いをします。
「とりあえず採用される可能性の高い求人を紹介する」ことはしません。
今の会社で「リーダー経験を積みたい」「顧客折衝に挑戦したい」「年収を上げたい」がかなわない時は、お気軽にご相談ください。